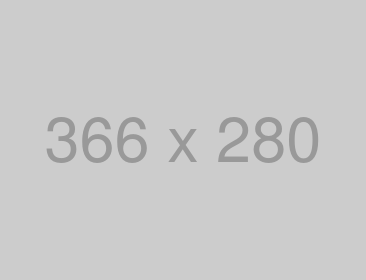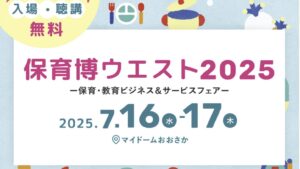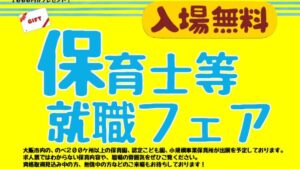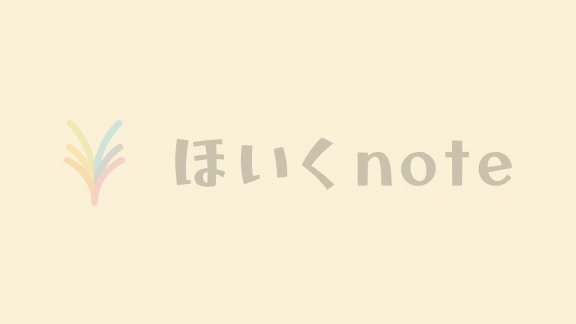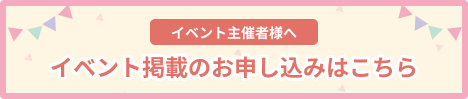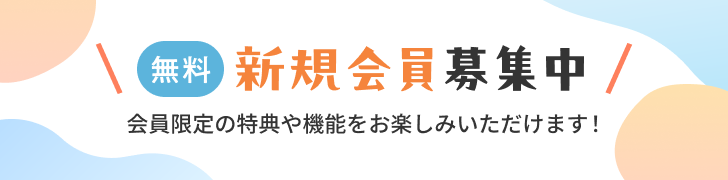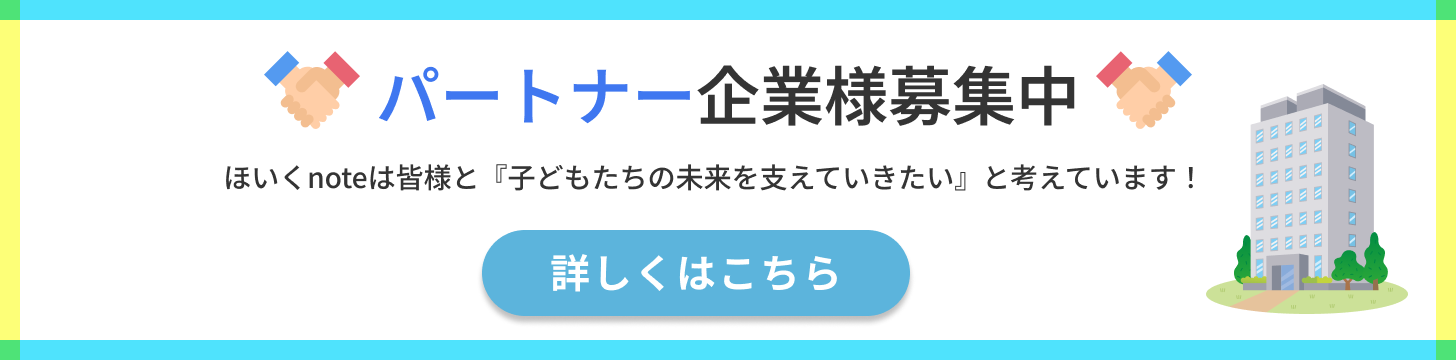こどもの遊びの意味を考える、こどもの世界がより深く理解できます。保育や子育てに直接役に立つことはないかもしれませんが、こどもの世界を知ることでより積極的にこどもと関われるようになるかもしれません。そんなきっかけになれば幸いです。
いないいないばあ
『いないいないばあ』は、こどもが大人と一番はじめに楽しむ遊びの一つです。こども番組のタイトルになるほど、こどもの遊びの基礎的なものだといえます。
こどもは、『いないいないばあ』をしてもらうことも好きですし、自分でやることも好きです。『いないいないばあ』を通じて、大人とこどもが笑いあい、肯定的な関係を深めていきます。
いないいないばあの本質

『いないいないばあ』は、なぜこどもにとって重要なのでしょうか。その本質は、いないことといることです。
ふだん私たちは、目の前にあるものが、例えば鞄に遮られて見えなくなったとしても、そのものが消えてしまったとは考えません。しかし、生まれたばかりの赤ちゃんはどうでしょうか?目
の前のものが隠されてしまうと、興味関心を失ってしまいます。まるで、消えてなくなったかのようです。『いないいないばあ』は、顔を隠します。それは、赤ちゃんにとって本当になくなっているのです。
いないいないで、大人が顔を覆うと、赤ちゃんにとって大人の顔が消えてなくなります。そしてばあ!でまた大好きな大人の顔が現れます。こどもは次第に大人が消えてもすぐ現れる安心感を体験します。どんな顔が現れるか興味が湧いて、『いないいなばあ』を繰り返し求めます。
自分でする場合も同じです。自分の世界から消えた大人が、自分のばあ!でまた現れます。まるで魔法ではないでしょうか!
かくれんぼ
『いないいないばあ』が発展すると、『かくれんぼ』ができるようになります。
この頃になると、大人が見えなくなっても消えてなくならないことは理解していますが、大人がいつでも自分を見てくれているかを心配しています。『かくれんぼ』をしても、大人が見つけてくれること、あるいは自分が出ていったら大人がすぐにむかえいれてくれること、このようなことを繰り返して、こどもは一人でいる力を培っていきます。
『いないいないばあ』や『かくれんぼ』を通じて、こどもは大切な存在が不在になってもまた現れることを理解していきます。こうした不在に耐える力が、こどもの心の強さや柔軟性につながっていきます。